|
大塩平八郎は、江戸時代後期の儒学者、陽明学者で、大坂町奉行組与力である。大塩家は代々、大坂東町奉行組与力であり、平八郎は初代の大塩六兵衛成一から数えて8代目にあたる。 |
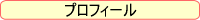
|
◆〔大塩平八郎〕のプロフィール。 |
|
大塩平八郎は、江戸時代後期の儒学者、陽明学者で、大坂町奉行組与力である。大塩家は代々、大坂東町奉行組与力であり、平八郎は初代の大塩六兵衛成一から数えて8代目にあたる。 |
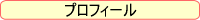
|
◆〔大塩平八郎〕のプロフィール。 |