|
日親は、応永14年(1407年)上総国で出生した、室町時代の日蓮宗の僧である。「不受不施義」を初めて唱えたとされる。 |
|
父親の実弟である日英に学び、中山法華経寺に入門する。応永34年(1427年)には上洛して、鎌倉や京都など各地で布教活動を行う。
『折伏正義抄』 |
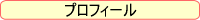
|
◆〔日親〕のプロフィール。 |
|
日親は、応永14年(1407年)上総国で出生した、室町時代の日蓮宗の僧である。「不受不施義」を初めて唱えたとされる。 |
|
父親の実弟である日英に学び、中山法華経寺に入門する。応永34年(1427年)には上洛して、鎌倉や京都など各地で布教活動を行う。
『折伏正義抄』 |
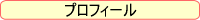
|
◆〔日親〕のプロフィール。 |