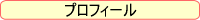| 通称 |
〔通称〕
・鈴木 大拙(すずき だいせつ)
|
| 本名 |
〔本名〕
・鈴木 貞太郎(すずき ていたろう)
|
| 別名 |
〔英語名〕
・D. T. Suzuki (Daisetz Teitaro Suzuki)
|
| 称号 |
〔称号〕
・文化勲章
・日本学士院会員
|
| 時代 |
〔時代〕
・明治時代~昭和時代中期
|
| 生誕 |
〔生誕〕1870年11月11日(明治3年10月18日)
〔生誕地〕石川県金沢市下本田村(現・本多町3丁目)
|
| 死没 |
〔死没〕1966年(昭和41年)7月12日)(95歳没)
〔没地〕東京築地聖路加病院
〔宗派〕臨済宗
〔墓所〕円覚寺の正伝庵
|
| 国籍 |
日本国 |
| 言語 |
日本語・英語 |
| 居住地 |
〔居住〕
・日本
・米国
・英国
・ドイツ
・スイスなど
|
| 学歴 |
〔学歴〕
・石川県専門学校初等中学科卒業
・第四高等中学校(現金沢大学)中退(予科卒業)
・東京専門学校(現早稲田大学)中退
・帝国大学(現東京大学)文科大学哲学科選科修了
・英語論文で大谷大学より文学博士号を取得
|
| 職業 |
〔職業〕
・教育者
・禅の研究者
|
| 分野 |
〔ジャンル〕
・禅の研究
|
| 所属 |
〔所属〕
・学習院講師(英語担当)
・東京帝国大学文科大学講師
・学習院教授
・大谷大学教授
・大谷大学教学研究所東亜教学部部長
・鎌倉に松ヶ岡文庫を設立
・ハワイ大学で講義
・コロンビア大学客員教授
・松ヶ岡文庫で研究生活
|
| 業績 |
〔業績〕
・禅についての著作を英語で著し、日本の禅文化を海外に広くしらしめた。
・鎌倉に松ヶ岡文庫を設立した。
|
| 作品 |
〔著作〕
『大乗起信論』
『大乗仏教概論』
『禅論文集1-3』
『浄土系思想論』
『禅思想史研究第一 盤珪禅』
『日本的霊性』
『臨済の基本思想』
|
| 受賞歴 |
〔受賞歴〕
・日本学士院会員
・文化勲章受章
|
| 名言 |
〔鈴木大拙の名言〕
・わしは死神と競走で仕事をする。
・仕事こそ人生なり。
・もっと他人を愛せ、悲ということは、他人を憐れむという本能的な事実から起こる。
・われわれは知性に生きるのではなく、意志に生きるのだ。
・死を恐れるのは、やりたい仕事を持たないからだ。やりがいのある、興味ある仕事に没頭し続ければ死など考えているヒマがない。死が追ってくるより先へ先へと仕事を続ければよいのである……
・人間は偉くならなくとも一個の正直な人間となって信用できるものになれば、それでけっこうだ。真っ黒になって黙々として一日働き、時期が来れば“さよなら”で消えていく。このような人間を偉い人だと自分はいいたい。
・昔、孔子が衣食足りて礼節を知るといったように、衣食住が充分でないと、その方面の要求を満たすに忙しくて、礼儀というようなことは行われぬ。礼儀ということは即ち文化ということである。
・エスキモーの生活というものは、極めて原始的なものである。今日我等の生活はこれに反して『文化的』である。
・エスキモー人の集団生活というものには、個人主義とか私有財産など云う概念がないと云うのです。一人が持って来たものは、みんなで分ける、みんなで食べる。一人だけで大事な物をこっそりと持って居るなどということがなくて、一つの集団に属したものとなって居る。
・自分の物もないし、人のものということもないので、その生活様式は本当に共産主義の生活である。
・原始民族が、魚を取って食べるとか、それからオットセイを食べるとかいう所を見ると、いかにも人間というものが生きて行くためには、又他の生物を食べて行かなければならぬ。
・今日文明開化の人々がなくてはならぬと云うようなものは、原始生活をして居るものには何も要らない。
・宗教生活にも原始生活の面影を宿したところがある。
・原始生活に教えられる所は、必要以外のものは絶対に何も要らないということ、そうしてお互いに共同融通して私を忘れるというような所である。
・道徳は宗教におき換へられねばならぬ。併し道徳から宗教は出て来ぬ、宗教からは道徳は出ることが出来る。
・道徳の世界にのみ居ては、宗教の世界へは入ること不可能である。
・一真実の世界は道徳の世界を超えて居る。
・道徳の世界は宗教の世界、禅の世界に引上げられねばならぬ。
・宗教の世界は、即ち禅の世界である、禅に入ることによってのみ、道徳の真実性が認められると云ってよいのである。
・悩みの解決は矛盾を超越するところに見られる。人間は反省する、分別する、矛盾を見る、悩むとすれば、その矛盾を超越するより外に解決の途はない。
・生死という形で、矛盾の問題を最も真剣に考えた民族は印度人である。彼等は生死を解脱すると云うことに、一所懸命であった。生死流転という文字は印度から出て東方諸民族の思想を支配するようになった。
・意識の世界は、不可避的に、制限と、道を阻む障壁とに充ちた世界である。
・それは常に意識の本質に相当する必然的一面性である。
|
| サイト |
|
| その他 |
・金沢時代の旧友である、安宅産業の安宅弥吉は「お前は学問をやれ、俺は金儲けをしてお前を食わしてやる」と約束し、大拙を経済的に支援したという。
|