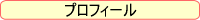| 通称 |
〔通称〕
・清少 納言(せいしょう なごん)
・現在では、一般に「せい しょうなごん」と発音されるが、「清」は父の性であり、「少納言」は職名に由来すると考えられるため、本来は「清 少納言」(せい しょうなごん)と発音するのが正しい。
・清=清原家出身
・少納言=身内に少納言という位の者がいた
|
| 本名 |
〔本名〕
・実名は不明
・諾子(なぎこ)という説があるが、実証する一級史料は現存しない。
|
| 別名 |
|
| 称号 |
|
| 時代 |
〔時代〕
・平安時代中期
|
| 生誕 |
〔生誕〕康保3年頃(966年頃)
〔生誕地〕東北地方
|
| 死没 |
〔死没〕万寿2年頃(1025年頃)
〔没地〕
〔墓所〕不明。墓所が各地に伝承される。
|
| 国籍 |
日本国 |
| 言語 |
日本語 |
| 居住地 |
|
| 学歴 |
|
| 職業 |
〔職業〕
・平安時代中期の女流作家・歌人・随筆家
〔活動期間〕
・990年代 - 1000年代
|
| 分野 |
〔ジャンル〕
・随筆
|
| 所属 |
〔家系〕
・梨壺の五人の一人である著名歌人 清原元輔の娘
・曽祖父は『古今和歌集』の代表的歌人清原深養父
|
| 業績 |
|
| 作品 |
〔代表作〕
『枕草子』
・『枕草子』は『源氏物語』と並ぶ中古文学の双璧であり、後世の連歌・俳諧・仮名草子に多大な影響を与えた。
・『枕草子』は、鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草』と並んで日本三大随筆と称される。
|
| 受賞歴 |
|
| 名言 |
〔清少納言の名言〕
・草の花はなでしこ。唐のはさらなり、大和のもいとめでたし。
(草の花は、なでしこ。唐なでしこはいうまでもない。大和のなでしこも、とてもすばらしい。)
・絵に描きおとりするもの なでしこ。菖蒲。桜。物語にめでたしといひたる男女の容貌(かたち)。
(絵に描くとつまらなくなるもの。なでしこ、しょうぶ、さくら。物語の中で、素晴らしいと書いてある男女の姿、形。)
・つれづれなぐさむもの 碁。双六。物語。三つ四つのちごの、物をかしう言ふ。
(所在なく退屈なのを慰めるもの、碁、双六。物語。三つ四つの幼児がものをおかしく言う。)
・ただ過ぎ過ぐるもの帆かけたる舟。人の齢。春、夏、秋、冬。
(どんどん過ぎていくもの。追い風に帆を張った舟。人の年齢。春・夏・秋・冬。)
・にくきもの、急ぐことある折りに来て長言する客人。
(不愉快なものは、急用のあるときにやってきて長話する客。)
・男こそ、なほいとありがたくあやしき心地したるものはあれ。いと清げなる人を捨てて、にくげなる人を持たるもあやしかし
(男ほど、滅多にないほど不可解な感情を持っているものはない。とても素敵な女性を捨てて、みるからにひどい女を恋人にするなんて、わけがわからない。)
・星はすばる。彦星。夕づつ。よばひ星すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。
(星といえば、すばる。彦星。宵の明星もいい。流れ星もそれなりに美しい。でも尻尾がなければもっといいのに。)
・遠くて近きもの 極楽。舟の道。人の仲。
・心地のあしく、物のおそろしきをり、夜の明くるほど、いと心もとなし。
(気分が悪く、なんだか不安なときは、夜が明けるまでがとても待ち遠しい。)
・常よりことに聞ゆるもの 正月の車の音。また、鳥の声。暁のしはぶき。物の音はさらなり。
(常とは異なって聞こえるもの。正月の車の音、また、鳥の声、暁の咳、ものの音色はさらに言うまでもない。)
・人にあなづらるるもの 築地のくづれ。あまり心よしと人に知られぬる人。
(人に軽く見られるもの。築地の崩れ。あまりにも性格が良いと人に知られてしまった人。)
・はづかしきもの 色好む男の心の内。
(恥ずかしいと感じるもの、女好きな男の心の奥。)
・雲は 白き。紫。黒きもをかし。風ふくをりの雨雲。明け離るるほどの黒き雲の、やうやう消えて、白うなりゆくも、いとをかし。「朝に去る色」とかや、詩にも作りたなる。月のいと明かき面に、薄き雲、あはれなり。
(雲は白い雲が良い。紫も、黒い雲も風情がある。風が吹く時の雨雲も良いもの。夜が明けきる頃の黒い雲が、少しずつ消えていってそらが白くなっていくのは、とても良いものです。「朝に去る色」とかいって、詩にもなります。月がとても明るいところに、薄い雲がかかるのも情緒があります。)
・冬は、いみじう寒き。夏は、世に知らず暑き。
(冬はとても寒いのがよく、夏は途方もなく暑いのがよい。)
・夜をこめて 鳥のそら音ははかるとも よに逢坂の関は許さじ。
(夜明けまえに、鶏の鳴きまねをしてだまそうとしても、この逢坂の関は決して許しませんよ。(あなたが逢いに来るのは決して許しませんよ))
・よろづのことよりも、情けあるこそ、男はさらなり、女もめでたくおぼゆれ
(他のどんなことよりも、情があることが、男はもちろんのこと、女でも素晴らしいことだと思われる)
・世の中に なほいと心憂きものは、人ににくまれんことことあるべけれ
(世の中で、やはりとても憂鬱なもの(嫌なもの)は、人に憎まれるということだろう。)
|
| サイト |
|
| その他 |
〔歌人〕
・中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人に数えられ、42首の小柄な家集『清少納言集』が伝わる。
・『後拾遺和歌集』以下、勅撰和歌集に15首入集。
〔伝墓所〕
・徳島県鳴門市里浦町里浦坂田
尼僧の姿で阿波里浦に漂着し、尼塚という供養塔を建てたという。
・香川県琴平金刀比羅神社大門
清塚という清少納言が夢に死亡地を示した「清少納言夢告げの碑」がある。
・京都市中京区新京極桜ノ町
誓願寺において出家、往生を遂げたという。
|