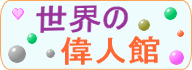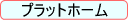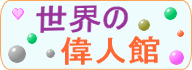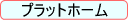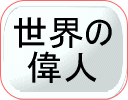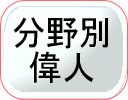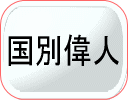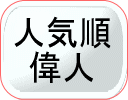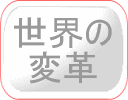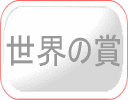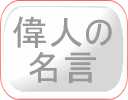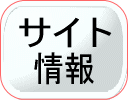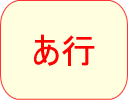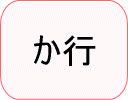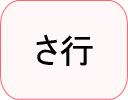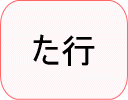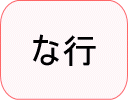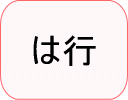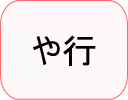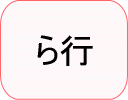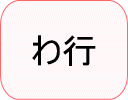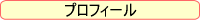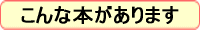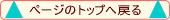こんな代表的な言葉があります。
つまづいたって
いいじゃないか
にんげんだもの
1924年に栃木県足利市で生まれ、旧制栃木県立足利中学校に通い、書や短歌、絵に親しんで勉学しました。ここを卒業後、歌人の山下陸奥に師事しました。
1942年のこと、歌会の席で、曹洞宗高福寺の武井哲応と出会い、生涯の師として仰ぐようになり、在家で禅を学びます。翌年には本格的な書家を目指すようになり、岩沢渓石に師事して書の修行を積みます。
1954年以降、書道家が憧れる書の最高峰とされる〔毎日書道展〕に7年連続入選を果たし、技巧派の書家として世に名を知らしめました。
1940~50年代、いわゆる古典書道の書を書いて実力を示しながらも、よほどの達人でなければ到底理解できないような古典書道のあり方に疑問を抱くようになり、「詩」の持ち味を、それに相応しい「書」によって表せないかと考えるようになり、「詩」と「書」の融合を目指すようになります。
こうして、味わいのある詩のこころを独特な書体で書く彼独特の作風を完成させたのでした。彼の作品では、短く平易な言葉が一種得得な雰囲気の書体で書き記され、人々の共感を誘います。
1950年代半ばころからは、足利市で盛んに個展を開くようになるのですが、やがて書だけでなく、ろうけつ染めも学び、風味豊かな暖簾などをデザインするようになります。
1984年になって、詩集『にんげんだもの』を出版し、ミリオンセラーとなります。主な作品には、詩集『おかげさん』『一生感動一生青春』『いのちいっぱい』『しあわはいつも』『アノネ』『空を見上げて』『大事なこと』『ひとりしずか』『雨の日には雨の中を風の日には風の中を』などがあります。
|