
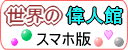



|
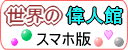
|
 
|
 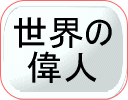 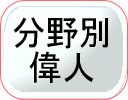 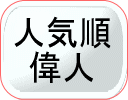 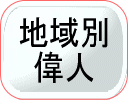 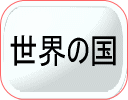 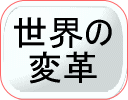 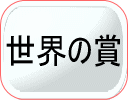 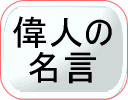 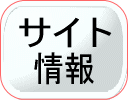 |
|
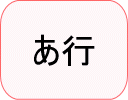 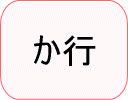 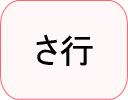  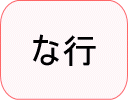 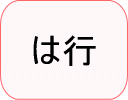  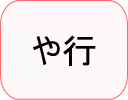 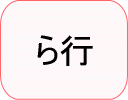 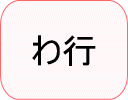
|
    
|
|
|||||||||||||||||||
|
徳川光圀は、水戸藩初代藩主徳川頼房の三男であり徳川家康の孫に当たり、水戸藩2代目藩主であり『水戸黄門』として知られる。  (出典:ウイキペディア)
儒学を奨励、彰考館を設け『大日本史』を編纂した。この書物編纂のために家臣を諸国に派遣したり、隠居後に水戸藩内を巡視したなどから、後世の『水戸黄門漫遊記』と呼ばれる逸話の主となった。 |
|
儒学を奨励し、彰考館を設けて、後に『大日本史』と呼ばれる修史事業に着手し、古典研究や文化財の保存活動など数々の文化事業を行い、水戸学の基礎をつくった。
さらに、徳川一門の長老として、徳川綱吉期には幕政にも影響力を持った。 |
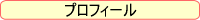
|
| プロフィール |
| 通称 |
〔通称〕 ・徳川 光圀(とくがわ みつくに) |
| 本名 |
〔本名〕 ・徳川 光圀(とくがわ みつくに) |
| 別名 |
〔別名〕 ・水戸光圀 ・水戸黄門 〔改名〕 ・長丸 ・千代松 ・徳亮 ・光国 ・光圀 〔諡〕義公 〔字〕子龍、観之 〔号〕日新斎、常山人、率然子、西山、梅里 〔神号〕高譲味道根之命 |
| 称号 |
〔栄典〕 ・従五位上左衛門督 ・従四位下右近衛権少将 ・従四位上右近衛権中将 ・従三位 ・参議 ・権中納言 ・贈従二位権大納言 ・贈従一位 ・贈正一位 |
| 時代 |
〔時代〕 ・江戸時代初期 |
| 生誕 |
〔生誕〕寛永5年6月10日(1628年7月11日) 〔生誕地〕水戸城下柵町(茨城県水戸市宮町) |
| 死没 |
〔死没〕元禄13年12月6日(1701年1月14日)(満71歳没) 〔没地〕 〔墓所〕 ・瑞龍山 ・久昌寺義公廟 ・常磐神社 |
| 国籍 | 日本国 |
| 言語 | 日本語 |
| 居住地 | |
| 学歴 | |
| 職業 |
〔職業〕 ・常陸水戸藩の第2代藩主 |
| 分野 | |
| 所属 |
〔藩〕 ・常陸水戸藩主 ・水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男で、徳川家康の孫に当たる。 〔氏族〕 ・徳川氏(水戸徳川家) |
| 業績 |
〔業績〕 ・藩主時代には寺社改革や殉死の禁止、快風丸建造による蝦夷地(後の石狩国)の探検などを行った。 ・後に『大日本史』と呼ばれる修史事業に着手し、古典研究や文化財の保存活動など数々の文化事業を行った。 ・儒学を奨励し、彰考館を設けて、後に『大日本史』と呼ばれる修史事業に着手し、古典研究や文化財の保存活動など数々の文化事業を行い、水戸学の基礎をつくった。 ・さらに、徳川一門の長老として、徳川綱吉期には幕政にも影響力を持った。 |
| 作品 | |
| 受賞歴 | |
| 名言 |
〔徳川光圀の名言〕
・ |
| サイト | |
| その他 |
水戸光圀は、その時代から、言行録や伝記を通じて名君伝説が確立している。江戸時代後期から近代には白髭と頭巾姿で諸国行脚して民百姓の味方をする物語上での黄門漫遊譚が確立する。 |
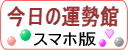  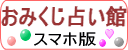
|
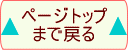
|